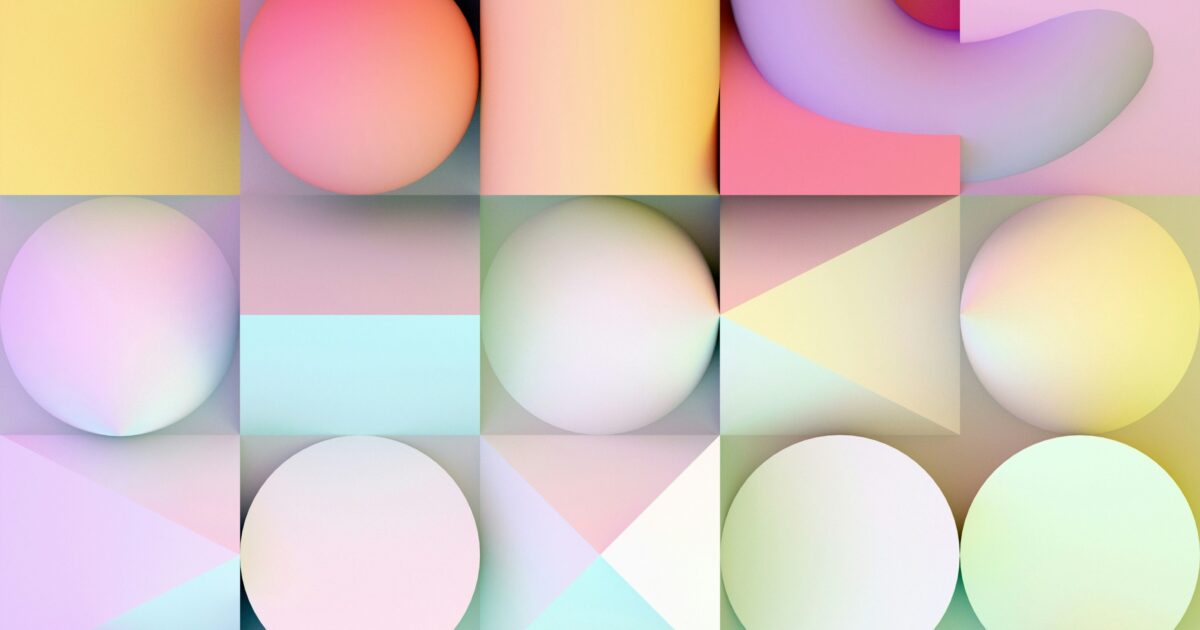DFT型NFTの導入を検討していると、設計や運用面で迷いが出ますよね。
構造や養液深、流速といった違いが分かりにくく、コストや保守負担の不安も大きいはずです。
この記事ではDFT型NFTの運用比較を、設計基準から日常保守、作物適正まで具体的に整理して不安を解消します。
構造や流速、養液管理、導入チェックリストなど主要項目ごとにメリット・デメリットと選定ポイントを提示します。
具体的にはポンプ仕様や配管、センサー校正、栄養補給頻度といった運用上の注意点も図表やチェックリストで分かりやすく解説します。
まずは要点を押さえた比較から始め、実務で使える設計・運用のヒントを次章で確認していきましょう。
DFT NFT 運用比較と主要項目
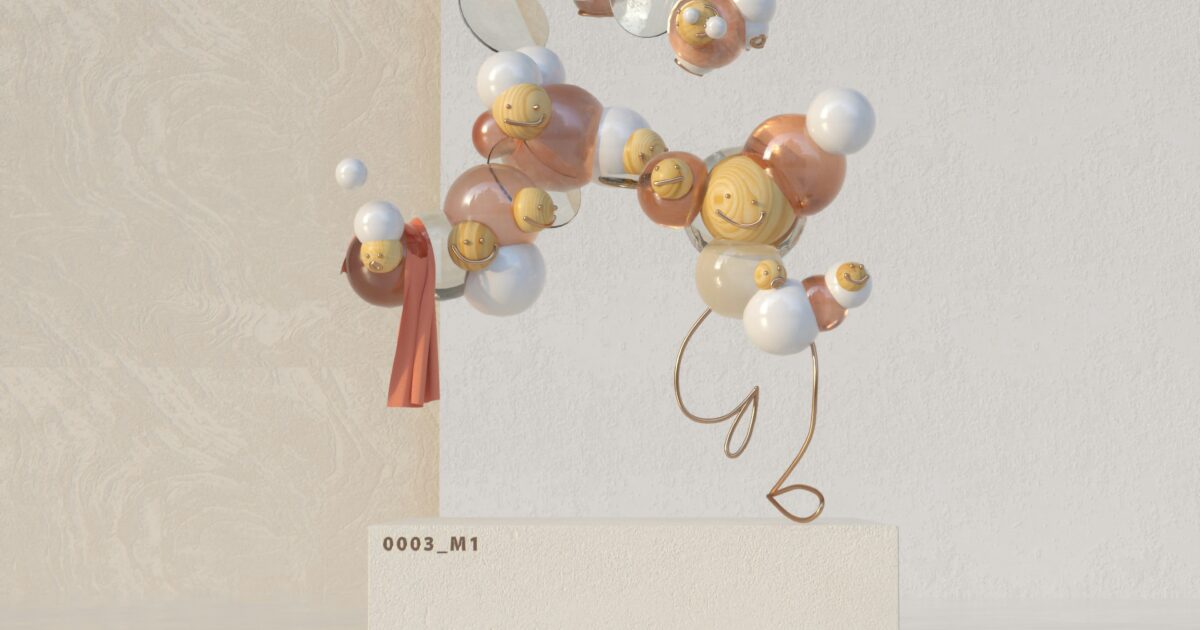
DFTとNFTはどちらも循環型の養液栽培方式ですが、構造や運用で大きく異なります。
ここでは主要項目ごとに比較し、現場での選定や運用に役立つポイントを整理します。
構造
NFTは薄い養液の膜がチューブやチャンネル内を連続的に流れる方式です。
流れる養液が根の先端に酸素と栄養を届けるため、トレーはわずかな勾配で設置されます。
DFTはより深い水位を保持するトレーに養液を安定供給する方式で、根圏が常に水に触れる時間が長くなります。
構造面ではNFTが細長いチャンネル構成を取り、DFTは平坦で深めのベッドを使う点が異なります。
養液深
一般的にNFTはごく薄い養液フィルムを前提とします。
養液の厚さは数ミリメートル程度を想定してください。
DFTは根が十分に浸かる深さを確保し、2センチから5センチ程度の水位を採ることが多いです。
深さが増すと養液の慣性が上がり、温度や酸素管理の重要性が増しますので注意が必要です。
流速
NFTは薄いフィルムを保つために連続的な流れが基本です。
流速は高すぎると根を傷め、低すぎると酸素不足になりますのでバランスが求められます。
DFTは循環頻度や流量を抑えた運用が可能で、間欠循環でも対応しやすい特徴があります。
いずれの方式でもポンプの冗長化や流路の均一化を検討すると安定性が高まります。
適用作物
方式ごとの得意分野がありますので、作物特性に合わせた選択が重要です。
- 葉物野菜 レタス 小松菜 サラダミックス
- ハーブ バジル ミント チャイブ
- 果菜類 小型トマト ミニトマト 一部のピーマン
- 根菜類 一部の小型根菜は不向き
NFTは根系が小さく酸素要求の高い葉物やハーブに向いている傾向があります。
DFTは根がやや大きい作物や、養液接触時間を長く取りたい場合に適しています。
設置コスト
初期投資の比較ポイントはトレー材質と配管の複雑さ、ポンプ容量です。
| 項目 | DFT | NFT |
|---|---|---|
| 初期費用 | 中程度 | 低め |
| 配管複雑さ | 簡易 | 複雑 |
| ポンプ要件 | 中程度 | 継続流が必要 |
| トレー素材 | 耐水性重視 | 軽量化が可能 |
表は一般的傾向を短く示したものです。
実際のコストは規模や素材選定で上下しますので、概算見積りを複数社から取ることを推奨します。
保守負担
NFTはチャンネルが狭いため、根やゴミによる詰まりが発生しやすいです。
定期的なチャンネル清掃とポンプの点検が欠かせません。
DFTは汚れが沈殿しやすく、底部の沈殿物対策や定期的な養液交換が重要になります。
どちらの方式でもアルジーやバイオフィルムの発生を抑える管理が保守負担の軽減につながります。
水質管理
ECとpHの安定化はどちらの方式でも基本です。
NFTでは薄膜のため養液の変動が早く、頻繁な測定が望ましいです。
DFTは容量が大きいため短期的な変動は緩和されますが、温度上昇や溶存酸素の低下に注意してください。
病害対策としては循環系の殺菌やろ過、センサーでの早期検知が有効です。
自動補正機器やアラーム設定を導入すると、人的ミスを減らし安定稼働につながります。
設計段階での選定基準

DFTやNFTシステムの成功は、設計段階での選定がほとんどを決めます。
導入後のトラブルを減らすために、設備レイアウトやポンプ仕様、養液循環方式、トレー素材を総合的に評価してください。
ここでは現場で後悔しないための実務的な選定ポイントをわかりやすく解説します。
設備レイアウト
まずは設置スペースと作業動線の確保が重要です。
トレイの配置は給排液の流れを最短にし、点検や収穫時の取り回しが良いことが望ましいです。
傾斜や勾配は養液の均一な流れを左右しますので、許容誤差を明確にしておいてください。
高低差や床荷重を考慮し、耐荷重床や架台の補強が必要かどうかも検討します。
照明や空調との干渉を避ける配置にし、将来的な拡張も視野に入れておくと安心です。
ポンプ仕様
ポンプは養液循環の心臓部であり、過不足のない能力選定が不可欠です。
必要な流量と揚程を算出し、運転条件に対して余裕を持った機種を選んでください。
耐食性やメンテナンス性、電力消費も運用コストに直結しますので注目します。
冗長化の要否や可変速運転の可否も、運用方針に合わせて決定してください。
| ポンプタイプ | 適用規模 | 目安流量 |
|---|---|---|
| 小型ダイアフラム | 家庭用ミニハウス | 50〜200 L/h |
| 遠心ポンプ | 中規模商用 | 200〜2000 L/h |
| サブマージブルポンプ | 水槽直置き | 100〜1500 L/h |
表を参考にして、現場の落差や配管長、運転時間に基づき最適なタイプを絞り込んでください。
養液循環方式
養液の循環方式は作物の生育安定性と水質管理のしやすさに直結します。
常時流しっぱなしの連続循環と、タイマーで間欠運転する方式にはそれぞれ長所短所があります。
- 連続循環
- 間欠循環
- リターン式循環
- バッチ式循環
選定にあたっては、作物ごとの根の酸素要求量やシステム容量を基準にしてください。
また、循環方式に応じてフィルターや殺菌ユニットの必要性が変わる点も見落とさないでください。
トレー素材
トレーの素材選びは耐久性と衛生管理に直結します。
一般的にはPVCやFRP、ステンレスが候補となり、耐薬品性や重量、コストを比較して決めます。
ステンレスは耐久性と洗浄性に優れますが、初期コストが高くなる傾向です。
一方でプラスチック系は軽量で安価ですが、長期的な紫外線劣化や薬液吸着を考慮する必要があります。
表面仕上げや接合部の水密性も、藻類発生や漏れを防ぐために重要なチェックポイントです。
導入時の施工と試運転手順

DFT NFTシステムの導入時には、施工の精度と試運転の丁寧さがその後の運用安定性を左右します。
ここでは据え付けから養液初期調整まで、現場で実行しやすい手順を段階的に説明いたします。
据え付け
設置場所の地盤レベルを確認し、支持フレームが平行に並ぶように仮組みを行ってください。
トレーやチャンネルの角度は極力揃え、養液が偏らないように水準器で微調整します。
架台やフレームは耐腐食性の処理がされていることを確認し、必要に応じてアンカーで固定してください。
電気配線や配管の取り回しは、作業動線とメンテナンス性を考慮して配置することをおすすめします。
配管接続
配管は薬品に強い材質を選び、接続部にはシール材やテフロンテープを適切に使用してください。
配管の傾斜を確保し、エアポケットが残らないように設計どおりに施工することが重要です。
- 配管径の確認
- バルブ配置
- 逆止弁の設置
- 漏水試験
- ドレン配列
接続後は一度クリーンな水でフラッシングを行い、施工時のゴミや油分を完全に除去してください。
ポンプ試運転
電源投入前に配線の接続とアースを再確認し、安全遮断装置が正常に動作するかを確認します。
低負荷でポンプを起動し、異音や振動がないかを観察してください。
| チェック項目 | 基準 |
|---|---|
| 流量 | 仕様値に一致 |
| 圧力 | 設定範囲内 |
| 異音 | 発生なし |
| 振動 | 許容値以下 |
ポンプの吸込み側に気泡が混入していないかを確認し、必要ならエア抜き作業を行ってください。
最終的にシステム全体の循環を行い、流路ごとの流量バランスを取ってから本運転へ移行します。
養液初期調整
初回の養液は薄めの濃度から始め、ECとpHを目標値へ徐々に調整してください。
苗や移植後の作物は環境変化に敏感ですので、初期は養液の交換頻度を高めに設定します。
pHは作物別の最適帯に合わせ、ECは生育段階に応じて段階的に上げる運用が安全です。
初期運転中はセンサー値を頻繁に記録し、目標値から逸脱があれば直ちに是正してください。
最後に漏水や配管接続部の緩みを再点検し、問題がなければ運用開始とします。
日常運用と保守管理項目
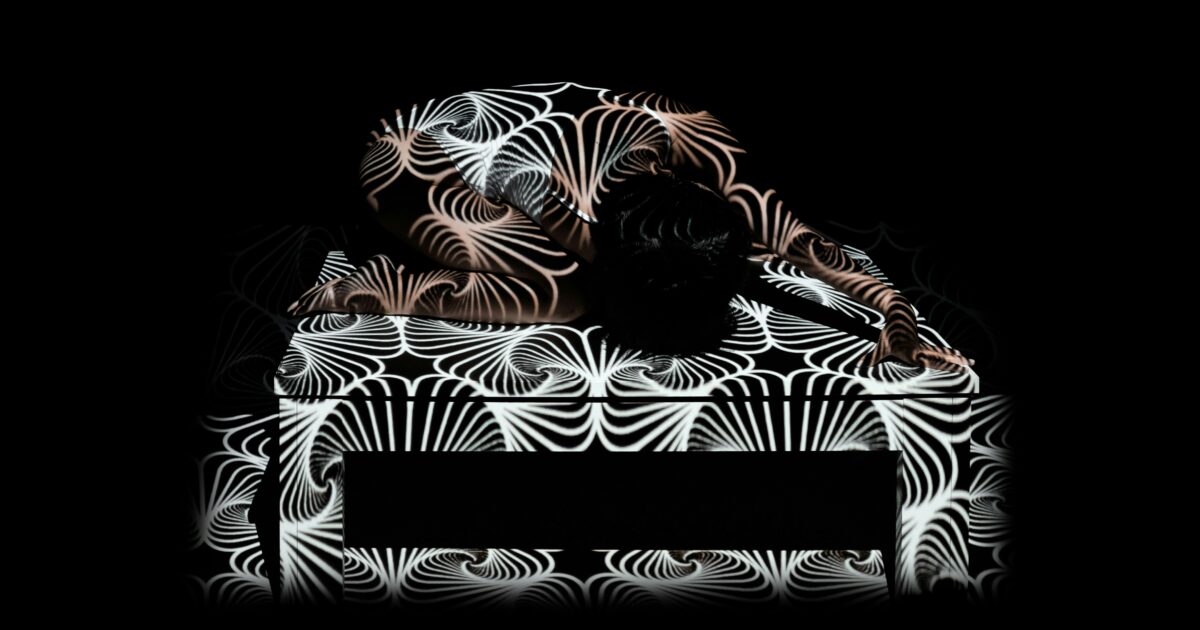
DFTやNFTのような養液栽培では、日常の運用と定期的な保守が生産性を左右します。
ここでは毎日の点検から週次の清掃、栄養補給の頻度、センサー校正、そして病害監視まで、実務で使えるチェックポイントを整理します。
日次点検項目
毎日の点検は作物の不調を早期発見し、養液トラブルを未然に防ぐための最も重要なルーチンです。
点検は朝の業務開始時と、必要に応じて午後にも行うのが望ましいです。
以下は日次で必ず確認したい項目です。
- 養液水位確認
- pHとECの簡易確認
- ポンプ作動確認
- 配管とトレイの漏水確認
- 照明と換気設備の動作確認
各項目は記録を残し、異常があれば直ちに詳細確認に移行してください。
週次清掃
週に一度の清掃は、スケールやバイオフィルムの蓄積を抑え、病原体の温床を減らすために有効です。
清掃作業は作物の生育段階に合わせて計画的に行う必要があります。
| 対象 | 作業内容 |
|---|---|
| トレイ | 洗浄すすぎ乾燥 |
| 配管 | フラッシング清掃 |
| ポンプ | フィルター点検交換 |
| 貯留槽 | 底泥除去消毒 |
清掃時は養液の全交換を検討し、洗浄後は適切に消毒を行ってください。
栄養補給頻度
栄養補給の頻度は作物の吸収速度と系内の循環量で決まります。
一般的な目安としては、葉物では3〜7日に一度、果菜類では2〜4日に一度の補給が推奨されます。
ただしECの低下が早ければもっと頻繁な補給が必要になります。
養液補給の際はまずECとpHを測定し、必要量を計算してから追加してください。
追肥は一度に大量投与せず、少量を複数回に分けると安定しやすいです。
センサー校正
pHやECセンサーは経時的にドリフトしますので、定期的な校正が欠かせません。
校正は最低でも月に一度、重要な生育期や異常を疑うときには週に一度行ってください。
校正には規定のバッファー溶液や標準溶液を使用し、取り扱いマニュアルに従って実施してください。
温度センサーや溶存酸素計も同様に定期点検と校正を行い、記録を残す習慣をつけてください。
病害監視
病害虫の早期発見は被害を最小限に抑える第一歩です。
毎日の目視点検に加え、週次で葉裏や基部のサンプルチェックを行ってください。
化学的防除を行う前に、粘着トラップや捕殺などの低負荷対策を試みると全体管理が安定します。
異常が見つかった場合は該当区画を隔離し、原因解析と対応記録を残してください。
データ管理と写真記録を組み合わせると、再発防止策の立案に役立ちます。
適合する作物分類
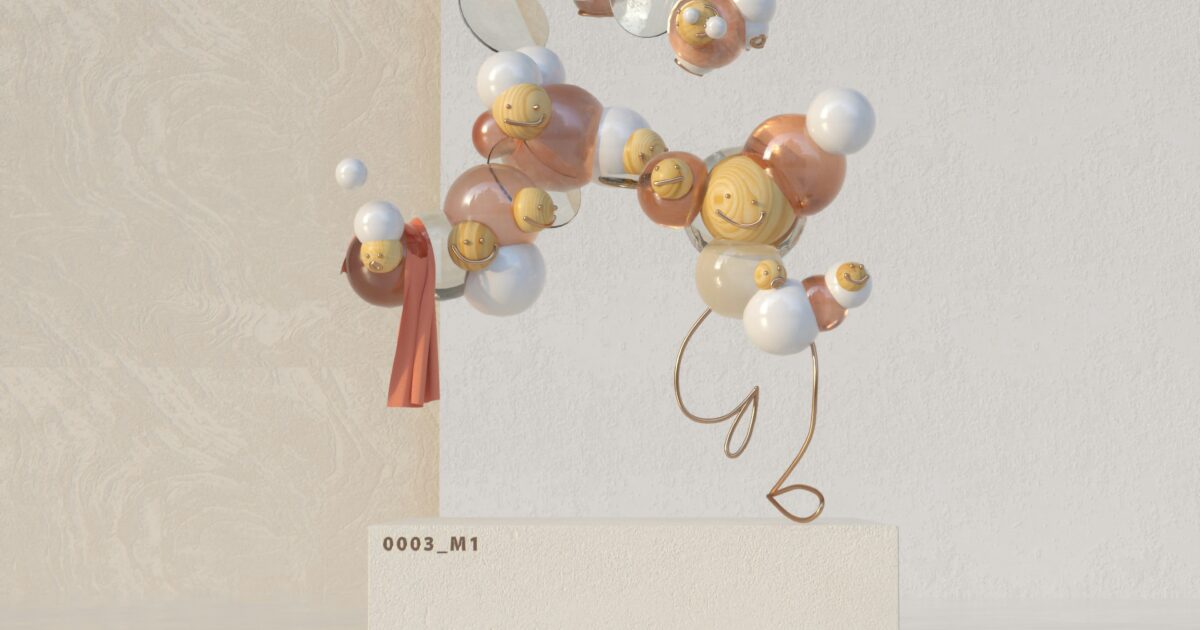
DFTやNFT方式は栽培対象によって向き不向きが明確に分かれます。
根の張りや生育速度、株間の取り方が運用負担や収量に直結します。
以下では主要な作物群ごとに適性と管理上のポイントを整理します。
葉物野菜
葉物野菜はNFT系システムとの相性が非常に良いです。
生長が早く、根系が比較的浅いため養液層の深さや流速の調整がしやすい利点があります。
- レタス
- ベビーリーフ
- ほうれん草
- 小松菜
密植が可能で、単位面積当たりの生産性を高めやすい点も魅力です。
ただし、葉面が大きくなる品種では風や光の不均一が品質低下を招くため環境制御が重要になります。
果菜類
果菜類は基本的に根系が大きく、支柱や人工授粉などの設備も必要になるためNFT単一での運用は工夫が求められます。
トマトやきゅうりなどの中~大型の果菜はトレーの剛性や養液補給方法を最適化することが前提です。
| 作物 | ポイント |
|---|---|
| トマト | 支柱管理必要 |
| きゅうり | 養液循環量多め推奨 |
| ナス | 根域確保重要 |
果菜類では養液の温度管理とEC変動の監視が特に重要になります。
開花期や結実期に栄養需要が増えるため、段階的なEC制御と頻繁な観察が必要です。
ハーブ
ハーブ類は種ごとの生育特性が多様ですが、全般的にNFTとの相性が良好です。
バジルやチャイブのような浅根性の品種は養液の薄さと速い循環に向いています。
香り成分の生成には日光と温度が影響するため、光環境を整えることが品質に直結します。
収穫のタイミングが短周期になるため、頻繁な剪定と追肥で高い回転率を実現できます。
花卉
切り花や鉢花などの花卉類は観賞価値を保つために均一な生育が求められます。
ペチュニアやインパチェンスなどの小型草花はNFTで良好に育つ場合が多いです。
一方で大きな球根や深根性の花卉は養液深が足りず不向きな傾向があります。
花卉栽培では病害予防と花形の保持を優先した水管理がカギになります。
環境制御によって開花時期を調整できれば付加価値を高めやすいでしょう。
導入可否判断のチェックリスト
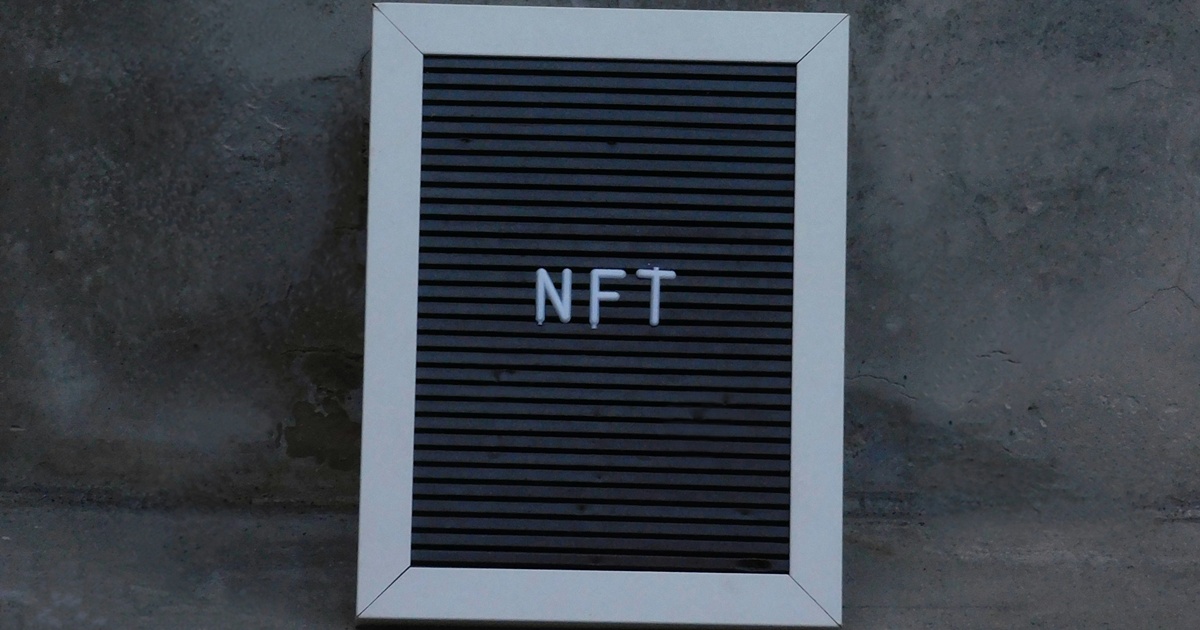
以下はDFTおよびNFT導入を検討する際の最低限のチェック項目です。
設備規模、作物特性、ポンプや配管の余力、養液管理体制、予算と保守要員の確保など、項目ごとに条件を満たすかを確認していきます。
- 設備スペースの確保
- 電源とポンプ余力の確認
- 作物適合性の評価
- 養液循環方式の選定
- 水質管理体制の整備
- 保守・清掃計画の有無
- 導入コストとランニングコストの試算
- 緊急時の排水・停止手順
- センサーと自動化機器の導入可否
- 労務体制と教育計画
リストで問題が明確になれば、試験導入から段階的に拡大する計画を立てることをおすすめします。